はじめに|中小企業診断士は独学?それとも予備校?
「中小企業診断士試験、どうやって勉強すればいいの?」
「完全独学でいける?やっぱり予備校に通うべき?」
「予備校ならTAC?LEC?それとも他の学校がいいんだろう…」
働きながら難関資格を目指すとき、誰もがこの「学習スタイルの選択」という壁にぶつかります。
限られた時間とお金を、どう使えば最も合格の可能性を高められるのか。教材選びや学校選びで、絶対に失敗したくない…。そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
こんにちは。「資格は人生のパスポート」の運営者です。私自身、会社員として働きながら中小企業診断士、社会保険労務士など複数の国家資格を取得してきました。(運営者プロフィールはこちら)
この記事では、私自身が「予備校の講義は受けず、TACの教材だけ」を活用して中小企業診断士にストレート合格した経験をもとに、あなたに最適な学習法を見つけるためのヒントを具体的にお伝えします。
この記事を読み終える頃には、あなたが「独学」と「予備校」のどちらを選ぶべきか、そして「なぜTACが有力な選択肢なのか」が明確になっているはずです。
【結論】私の場合は「TACの教材を利用した独学」が最適解でした
最初に私の結論をお伝えします。それは、**「完全な独学」でも「予備校にフルで通学」するのでもなく、両方の“良いとこ取り”をした『TACの教材をペースメーカーにした独学スタイル』**でした。
なぜこの方法を選んだのか?理由は3つあります。
- 理由1:学習のペースを自分で管理したかった
仕事の繁忙期などを考えると、決まった時間に講義を受けるスタイルは不向きでした。
- 理由2:教材選びで失敗したくなかった
独学で最も怖いのが「教材の質」。市販の教材を買い集めても、内容に漏れや重複が生まれるリスクがありました。実績のある予備校の教材なら、その心配がありません。
- 理由3:独学の弱点を補強したかった
特に2次試験の記述対策など、客観的なフィードバックが必要な部分だけは、予備校のサポート(答練や模試)を活用したいと考えました。
この考えを元に、いくつかの予備校を比較検討した結果、最終的にTACを選びました。
なぜ他の予備校ではなくTACを選んだのか?【LEC・大原とも比較】
中小企業診断士の予備校といえば、TAC、LEC、大原などが有名です。私も実際に各校のパンフレットを取り寄せ、比較検討しました。あくまで私個人の見解ですが、当時の印象は以下の通りです。
| 予備校 | 特長(個人的な印象) |
| TAC | 教材の網羅性と質の高さが際立つ。合格実績No.1の信頼感。良くも悪くも王道で、教材に沿ってやれば合格レベルに達せるという安心感があった。 |
| LEC | 2次試験対策に定評があり、独自の解法メソッドが有名。合う人には非常に強力な武器になるが、私には少しクセが強く感じられた。 |
| 大原 | 簿記や税理士などの会計系資格に強いイメージ。中小企業診断士講座も質は高いが、当時はTACほどの実績や教材の洗練度は感じられなかった。 |
最終的に私がTACを選んだ決定的な理由は、「教材だけで学習が完結できるほどの網羅性と分かりやすさ」そして「全国の校舎にある自習室の利用」という2点です。
講義を受けない私にとって、教材の質は何よりも重要でした。そして、家では集中できない時に使える自習室の存在は、学習効率を維持する上で大きな魅力だったのです。
【私の体験談】講義なしでTACの教材を使い倒した具体的な勉強法
ここがこの記事の核心部分です。私が実際に、講義なしでTACの教材をどう使いこなし、ストレート合格を勝ち取ったのか、具体的な勉強法をご紹介します。
1次試験:基本テキストと問題集をひたすら繰り返す
1次試験の基本は、とにかくインプットとアウトプットの繰り返しです。私が徹底したのは以下のルールでした。
- 浮気しない:市販の参考書には手を出さず、TACの「スピードテキスト」と「スピード問題集」に絞りました。
- 最低5回転:全7科目、問題集は最低でも5回は繰り返しました。間違えた問題には付箋を貼り、翌週・翌月にもう一度解く、というサイクルを徹底しました。
- スキマ時間を活用:通勤電車の中では、スマホアプリではなく、問題集をコピーしてファイリングしたものを読み込んでいました。重たいテキストを持ち歩く必要がなく、非常におすすめです。
2次試験:「答練」の添削で“書く型”を叩き込む
独学最大の鬼門、2次筆記試験。私がこれを乗り越えられたのは、間違いなくTACの**「答練(答案練習)」**のおかげです。
独学では「自分の解答が本当に正しいのか?」という客観的な評価ができません。しかしTACの答練は、採点基準が非常に明確で、どこで部分点を取れ、なぜ減点されたのかが一目瞭然でした。返却された答案の真っ赤な添削を見るたびに、自分の思考のズレを修正していきました。
この添削を何度も繰り返すことで、**「出題者の意図を読み取り、加点されるキーワードを盛り込み、論理的に文章を構成する」**という、合格点を取るための「型」を体に叩き込むことができたのです。
学習スケジュール:平日2時間、休日6時間を確保
働きながらの勉強は、時間の捻出がすべてです。私は「朝方」に切り替え、以下のスケジュールで学習を進めました。
- 平日:朝5時に起床し、出社前の2時間を勉強に充てる。夜は無理せず、早く寝る。
- 休日:午前中に3時間、午後に3時間の計6時間を確保。時にはTACの自習室を利用して集中力を高めました。
この生活を試験直前まで約1年間続けました。決して楽ではありませんでしたが、TACのカリキュラムが良いペースメーカーとなり、挫折することなく走りきることができました。
改めて解説!中小企業診断士の学習でTACをおすすめする3つの理由
私の体験談を踏まえ、改めてTACが中小企業診断士の学習においてなぜ強力な選択肢となるのか、理由を3つに整理しました。
1. 教材の質と網羅性(独学でも挫折しない設計)
最大の強みは、やはり教材の質の高さです。過去の試験を徹底分析して作られたテキストと問題集は、これだけで合格に必要な知識が網羅されています。「何を、どの順番でやればいいか」が明確なので、独学でも迷うことなく学習を進められます。
2. 集中できる学習環境(全国の自習室)
TACの受講生になると、全国の校舎にある自習室が利用可能になります。静かで集中できる環境は、自宅学習が苦手な方にとって絶大な効果を発揮します。私も出張先で現地の自習室を利用するなど、フル活用させていただきました。
3. 圧倒的な合格実績と最新情報への対応力
長年の実績は、信頼性の証です。事実、2024年度の試験では、私の後輩が2人合格しました。ひとりはTACの講座に通って、もうひとりは私と同じようにTACの教材(スピードテキスト等)を活用した独学でした。どちらのスタイルでも結果が出せるのは、カリキュラムと教材が優れているからに他なりません。
まずは情報収集から!無料の資料請求で学習戦略を立てよう
ここまで読んで、「TAC、少し気になるかも」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、予備校選びは大きな投資です。いきなり申し込むのではなく、まずはご自身の目で「本当に自分に合っているか」を確かめることが重要です。
TACでは、講座の詳しいカリキュラムや教材のサンプルがわかる資料を無料で取り寄せることができます。
- どんな教材で学習するのか?(実際のテキストサンプル)
- 1年間の学習スケジュールは?
- 合格した先輩たちのリアルな体験談
といった、公式サイトだけではわからない情報が満載です。この資料に目を通すだけでも、中小企業診断士試験の全体像が掴め、ご自身の学習戦略を立てる上で非常に役立つはずです。
無理な勧誘なども一切ありませんので、まずは気軽に情報収集の一環として活用してみてはいかがでしょうか。
→ TACの無料資料請求で学習のヒントを得る まとめ|合格への道は正しい教材選びから
今回は、私の実体験をもとに中小企業診断士試験の学習法について解説しました。
働きながらの資格取得は、間違いなく「戦略」が重要です。そしてその根幹をなすのが「教材選び」。この記事が、あなたの最適な教材選び、そして合格への第一歩を踏み出すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
当サイトでは、他にも資格取得に役立つ情報を発信しています。よろしければ、こちらの記事もご覧ください。
→【関連記事】中小企業診断士試験|合格までの勉強時間は?【独学】

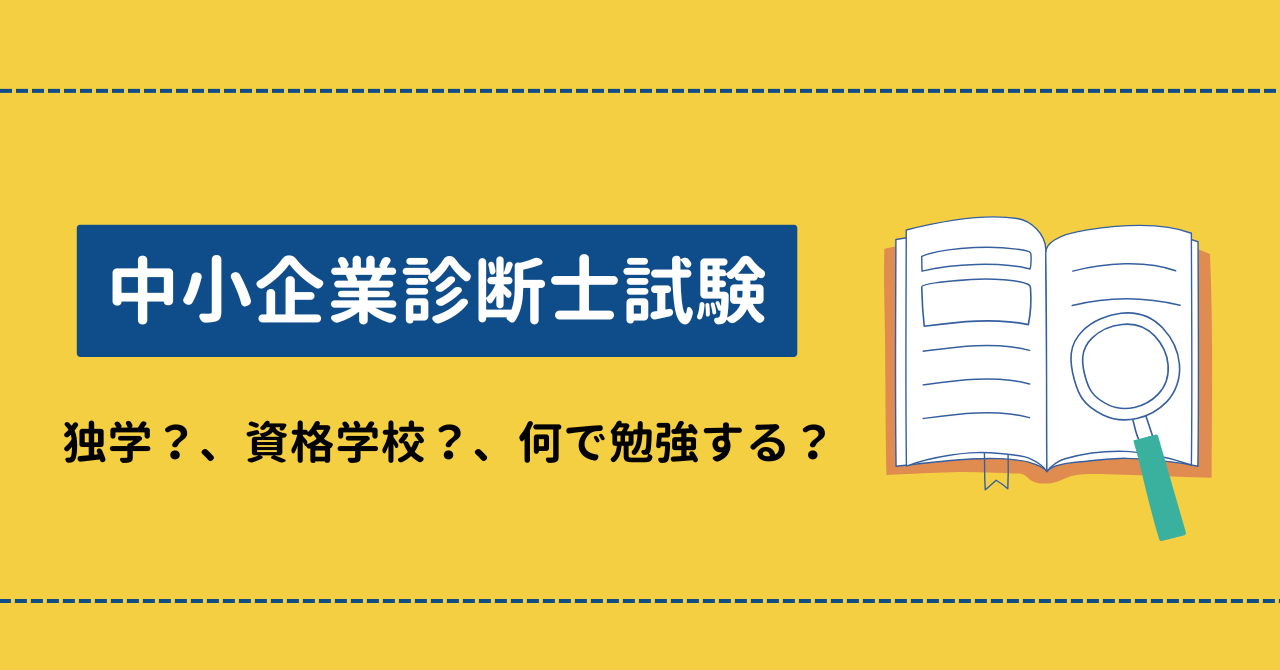






コメント