はじめに|育児・転勤でも中小企業診断士に独学ストレート合格!
「仕事や育児で忙しいけど、本当に中小企業診断士に独学で合格できるの?」
そんなあなたの不安を、私のリアルな体験で解消します。
はじめまして。私は、働きながら中小企業診断士試験に1年でストレート合格(1次・2次試験を同年度に合格)しました。しかも、合格までの1年間は、長男の誕生、未経験業務への転勤、引っ越しなど、人生の大きなライフイベントが立て続けに起こる、まさに激動の時期でした。
限られた時間と厳しい環境の中、最終的に555時間の学習で合格まで辿り着きました。
この記事では、単なる勉強時間の記録だけでなく、多忙な中でも時間を捻出し、効率的に学習を進めた具体的な方法を余すところなくお伝えします。
「働きながら」「家庭と両立しながら」合格を目指すあなたにとって、「これなら私でもできる!」と、明日からの学習のモチベーションにつながるはずです。
この記事を読めば分かること
- ライフイベントと両立したリアルな総勉強時間
- 【真似できる】忙しい毎日から勉強時間を捻出する5つの具体策
- ストレート合格を可能にした効率的な学習戦略と時間配分
- 短期決戦で乗り切った2次試験の対策ポイント
中小企業診断士の合格に必要な総勉強時間について、475時間は1次試験合格、最終合格に必要な時間は555時間でした。
当初は1次試験だけで650時間を見込んで計画を立てていましたが、予期せぬライフイベントの連続で、計画を大幅に下回る結果に。しかし、これが逆に「時間がないからこそ、学習の質を高めよう」という意識改革につながりました。
中小企業診断士試験は、1000時間以上の勉強が必要と言われることもありますが、必ずしも時間の長さが合否を決めるわけではありません。限られた時間をいかに有効活用するか。その「戦略」こそが、短期合格の鍵だと断言します。
【この記事の核心】多忙な社会人が勉強時間を捻出した5つの具体策
「わかってはいるけど、その時間がないんだ…」という声が聞こえてきそうです。私もそうでした。そこで、私が実践した「平日2時間、休日6時間」を確保するための具体的なテクニックをご紹介します。これが、今回の記事で最もお伝えしたい部分です。
① 朝の1時間を「思考のゴールデンタイム」に
誰にも邪魔されない朝5時〜6時の1時間は、最も頭がクリアな「思考のゴールデンタイム」です。私はこの時間を、経済学や財務・会計など、深い思考と理解が求められる科目の学習に充てました。夜の疲れた頭で取り組むより、効率が2倍にも3倍にも感じられました。
② 往復2時間の通勤を「動く書斎」に変える
往復2時間の通勤時間は、絶好のインプット時間です。スマホで試験対策のメモを見直します。「通勤時間はインプット」と割り切ることで、インプット不足の不安が解消されました。
③ 昼休み30分を「記憶の定着タイム」に
昼休みは1時間。食事はカフェにして、15分で食べて、残り時間を朝に学んだ内容の過去問演習にあてるというルールを設けました。移動時間を差し引いても残り時間は30分あるので、5~10問は解くことができます。短い時間でもアウトプットを挟むことで、知識の定着率が格段に上がります。「思い出す」という行為が、記憶を強固にしてくれるのです。
④ 子供の寝かしつけ後を「最後の追い込み時間」に
夜は疲れているため、複雑な学習には向きません。そこで、暗記系の科目(経営法務、経営情報システムなど)の要点チェックや、その日に間違えた問題の復習に特化しました。学習のハードルを下げることで、疲れていても机に向かう習慣を維持できました。
⑤ 家族との時間を確保するための「やらないことリスト」
勉強時間を確保するために、何かを犠牲にする必要がありました。そこで私は「やること」ではなく**「やらないこと」**を決めました。例えば、「平日のテレビやYouTubeは観ない」「意味のない飲み会には参加しない」などです。これにより生まれた時間と精神的な余裕を、勉強と家族サービスに振り分けることができました。特に、妻の協力なしに合格はあり得ませんでした。感謝しかありません。
Excel公開!1次試験475時間の科目別・月別リアルな内訳と戦略
学習の進捗は、自作のExcelですべて「見える化」していました。記録することでモチベーションが維持でき、科目ごとのバランス調整にも役立ちました。
実際に使用していたExcelはこちら。
](https://shikakupassport.com/wp-content/uploads/2025/03/image.png)
科目別の最終的な勉強時間はこちらです。
](https://shikakupassport.com/wp-content/uploads/2025/03/image-1.png)
この記録から、「財務・会計」と「運営管理」に時間を要していることが分かります。これらは2次試験にも直結する重要科目であるため、重点的に時間を投入しました。一方で、暗記が中心の「経営法務」や「経営情報システム」は、スキマ時間を活用して効率的に学習を進める戦略を取りました。このように、科目特性に合わせて学習スタイルを変えることも、短期合格のポイントです。
2次試験対策は80時間!短期集中で乗り切った3つのポイント
1次試験後の自己採点で合格を確信したものの、転勤や引っ越しで全く時間がなく、本格的な2次対策を始められたのは試験の1ヶ月半前からでした。学習時間の記録はつけられませんでしたが、体感では約80時間。超短期決戦を乗り切るために、以下の3点に絞って対策しました。
- 解法プロセスの型を作る
過去問を解き、「与件文の読み方 → 設問解釈 → 骨子作成 → 記述」という一連の流れを自分の中でパターン化(型化)しました。本番で焦らないための、思考の拠り所を作ったのです。 - 模試を本番と捉える
たった1回の模試を「本番」と位置づけ、時間配分や解法プロセスの「型」が通用するかを徹底的にシミュレーションしました。この模試の復習が、最も学習効果が高かったです。 - 他の受験生がどのような視点で、どんなキーワードを使って解答しているのかを徹底分析しました。自分に足りない視点や表現をインプットし、解答の精度を高めていきました。
まとめ|時間の工夫で中小企業診断士試験は合格できる!
中小企業診断士試験は難関ですが、働きながら、家庭と両立しながらでも、工夫次第で短期合格は十分に可能です。
合格までの道のりを振り返って痛感するのは、「勉強時間の長さ」よりも「確保した時間の使い方(質)」が何よりも大切だということです。確保できない時間を嘆くよりも、今ある時間で最大の成果を出す方法を考えましょう。
- スキマ時間をかき集め、目的別に使い分ける
- 学習の優先順位をつけ、重要科目に集中する
- 学習を記録して、モチベーションを維持する
- 家族の理解と協力を得て、勉強に集中できる環境を作る
この記事で紹介した時間捻出術が、あなたの状況に合わせてアレンジされ、合格への一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
あなたの努力が実を結ぶことを、心から応援しています!
関連記事|合わせて読むならこちら!
【体験談】TAC教材だけで中小企業診断士に合格した私が語る独学・予備校の選び方
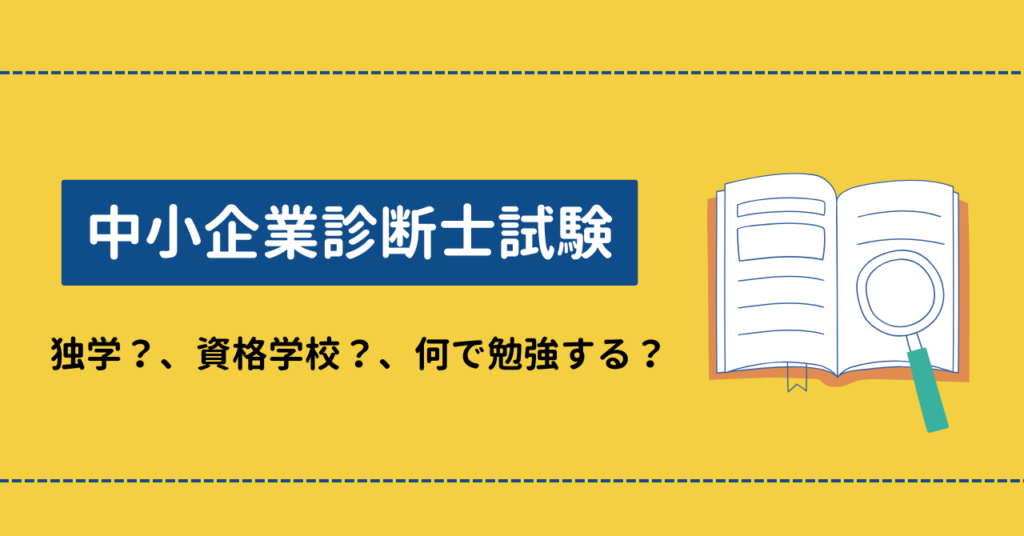


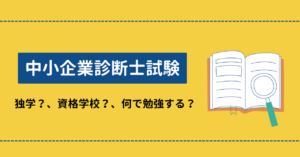





コメント