言語聴覚士(ST)は、医療・介護・福祉・教育など幅広い分野で活躍する国家資格職です。その専門性の高さから、多くの責任と期待が求められる現場も少なくありません。
「患者に良くなってほしい」という思いが強いほど、思うように成果が出なかったり、職場の人間関係に悩んだりすると、大きなストレスにつながることがあります。
特に若手や中堅STは、キャリアの過渡期において精神的に不安定になりやすい時期でもあります。
本記事では、言語聴覚士が直面しやすいストレスの要因や、メンタルヘルスケアの具体的な方法、働き続けるために必要な自己調整のスキルなどを、実例とともに詳しく解説します。
言語聴覚士が感じやすいストレスの原因
1. 患者との関係からくるプレッシャー
STは患者の「できるようになりたい」「治りたい」という強い希望を受け止めながら、その支援をしていく職種です。しかし、症状によっては劇的な回復が見込めなかったり、訓練の成果が出にくい場合もあります。
そうした状況に対し、「自分の指導が悪いのでは」「もっと良い方法があったのでは」と、自責的に考えてしまうSTも多くいます。
2. 多職種連携・人間関係の難しさ
病院や施設では、PT(理学療法士)やOT(作業療法士)、看護師、介護士、医師などと連携して仕事を進める必要があります。
それぞれの職種の立場や考え方の違いから、コミュニケーションや情報共有にストレスを感じる場面も少なくありません。
3. 評価や結果を求められる環境
臨床では「何ができるようになったか」「効果は出ているか」といった明確な成果が求められがちです。
短期間での結果が出にくい高次脳機能障害や失語症のリハビリでは、努力が数値化されにくいため、やりがいを見失ってしまうこともあります。
4. 自分のキャリアへの不安
数年働くと「このままの働き方で良いのか」「この先もずっと臨床でやっていけるのか」といった将来への不安が現れてきます。特に昇進や専門性の明確なステップが少ない職場では、自分の価値を見出しづらいという悩みに繋がります。
メンタルケアの具体的な方法
1. 同僚・仲間と気持ちを共有する
職場での悩みやストレスを一人で抱え込まず、同僚や先輩、他職種の仲間に話してみましょう。共感や助言が得られるだけでなく、「自分だけじゃない」と感じることで気持ちが軽くなります。
2. 専門職としての限界を理解する
全ての症状に改善をもたらすことはできません。
「自分の責任範囲」と「自然経過や他要因による限界」を明確に分けて考えることで、必要以上に自分を責めずに済むようになります。
3. ワークライフバランスの見直し
長時間勤務や休日返上が続くと、心も体も疲弊してしまいます。趣味・運動・睡眠・家庭など、プライベートの充実もメンタルの安定には欠かせません。
「仕事以外に心の拠り所を持つこと」が、回復力を高めます。
4. 専門家への相談を検討する
どうしてもつらい状態が続く場合には、医療機関の心療内科やEAP(従業員支援プログラム)などの外部サポートを活用しましょう。
早めの対処が、心身の悪化を防ぎます。
燃え尽き症候群(バーンアウト)に注意
バーンアウトは、強い責任感と理想を持つ人ほど陥りやすいといわれています。
主な兆候には以下のようなものがあります。
- 仕事に対する意欲の低下
- 遅刻・欠勤・早退が増える
- 感情の起伏が激しくなる
- プライベートでも楽しめない
- 体調不良(頭痛・吐き気・不眠など)が続く
このような状態になったときは、「少し休む」ことも大切な選択です。
「休むことは悪いことではない」と、まずは自分を許すことから始めましょう。
自分らしいキャリア形成が心の安定を支える
多様な働き方を知ることで、未来への不安が減る
臨床以外にも、教育、研究、訪問、自費サービス、オンライン支援など、STの可能性は広がっています。
小さな成功体験を積み重ねる
「1回のセッションで声が少し出た」「患者が笑顔を見せてくれた」など、日々の些細な成功を見逃さないこと。
ポジティブな記録をつける習慣もおすすめです。
まとめ:心の健康も、スキルと同じくらい大切
STは「人に寄り添う」仕事であるからこそ、自分自身の心のケアをおろそかにしてはいけません。
ストレスや燃え尽きを防ぐには、日頃から自分の状態に気づき、必要な対処をとる力が重要です。そして、職場環境だけでなく、「自分がどう働きたいか」を見つめ直すことが、長く安心して働ける道へとつながります。
あなたが言語聴覚士として輝き続けるために、心の健康にもぜひ目を向けてみてください。

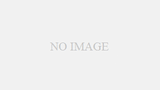
コメント