言語聴覚士(ST)というと、病院や介護施設などでの臨床業務をイメージする方が多いかもしれません。確かに、現場で患者と向き合う仕事はSTの中心的な役割です。
しかし、STのキャリアはそれだけではありません。近年では、大学院への進学や研究職への道を歩むSTも増えており、「科学的根拠に基づいた支援」や「言語・聴覚に関する知見の深化」を目指すキャリア形成が注目されています。
この記事では、臨床経験を活かして研究・教育の道へ進むための具体的なステップや、大学院進学に必要な準備、研究職STの働き方について詳しく解説します。
なぜ言語聴覚士が研究職を目指すのか?
臨床だけでは解決できない課題の存在
現場での支援を通じて、対応が難しいケースや、エビデンスが不足している領域に直面することは少なくありません。そうした課題に対して、「研究というアプローチで根拠を見つけたい」と考えるSTが増えています。
社会的なニーズの高まり
高齢化や発達障害の早期発見ニーズの拡大に伴い、言語や聴覚の専門的な研究成果が、行政・教育・医療に活用される機会が増えています。
臨床にとどまらず、政策立案や教材開発に関わるSTの役割も期待されています。
大学院進学のメリットと目的
知識の体系化と専門性の深化
大学院では、言語発達、音声学、失語症、摂食嚥下、認知症、発達障害など、特定分野における学術的理解を深めることができます。
研究スキルの習得
文献検索、統計解析、研究計画の立案、学会発表、論文執筆といったスキルを体系的に学ぶことで、臨床の質も高まります。
キャリアの幅が広がる
大学・専門学校の教員、公的研究機関、自治体との共同研究、コンサルティング業務など、大学院修了後は多様な道が開けます。
大学院進学に向けた準備
① 研究テーマの選定
臨床経験から「もっと知りたい」と思った疑問をテーマに昇華させることが、モチベーション維持にもつながります。
② 指導教員の選定とアプローチ
大学院は「誰に学ぶか」が非常に重要です。興味ある研究分野を持つ教員を探し、研究室の方針や過去の研究内容を調べた上で、事前にコンタクトを取ることが望ましいです。
③ 入試対策(小論文・面接・英語)
社会人経験者枠を設けている大学院もありますが、基本的な論文読解や記述、研究計画のプレゼン力などが求められます。
事前に大学院入試の過去問や参考書で準備しておきましょう。
研究職STのキャリアモデル
モデルケース1:臨床経験5年 → 大学院修士課程 → 大学教員
STとして急性期病院で勤務後、失語症のリハビリについて探求したいという想いから大学院へ進学。修士課程修了後、専門学校での非常勤講師からスタートし、大学の専任教員へ。
モデルケース2:訪問リハ勤務中 → 博士課程 → 自治体と共同研究
地域リハの実態をデータで示す必要性を感じ、大学院博士課程に進学。地域包括ケアにおけるSTの役割に関する研究を自治体と協働で進め、現在は行政のリハビリ政策に助言する立場に。
大学院進学の現実と注意点
経済的・時間的コスト
社会人での進学は学費・生活費の確保が課題です。働きながら通える夜間・通信制や、奨学金、リサーチアシスタント制度の活用も視野に入れましょう。
研究と臨床の両立の難しさ
どちらも中途半端にならないよう、計画的に時間を使い、ストレスマネジメントも必要です。家族の協力や職場の理解も得ておきましょう。
目的を明確にすることが鍵
「とりあえず進学」ではなく、「何を明らかにしたいのか」「将来どう活かすか」を明確にすることで、進学後の道筋がクリアになります。
まとめ:STの可能性を広げる“学び直し”という選択
研究職を目指すことは、臨床の現場で感じた課題や疑問を、学術的アプローチで深めるという意味で、非常に意義のあるキャリアです。
現場経験があるSTだからこそ見える課題があります。そして、その課題を言語化し、データに基づいて検証するスキルを身につけることで、STとしての価値と影響力は大きく広がります。
「いつか研究をしてみたい」と思っているなら、その気持ちを育て、具体的なアクションに移してみてはいかがでしょうか?

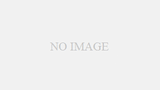
コメント