言語聴覚士(ST)として働き始めて数年。日々の臨床業務にも慣れ、自信を持って患者対応ができるようになってきた方も多いことでしょう。そんな中、「このままで良いのだろうか?」「5年後・10年後、自分はどこで何をしているのだろう?」と不安や迷いを感じ始めていませんか?
STは専門職である一方、明確なキャリアのロードマップが存在しにくい職種でもあります。そのため、自分自身で未来を設計し、行動していくことがとても重要です。
本記事では、「5年後」「10年後」に向けてどのようなキャリアビジョンを描き、何を準備すれば良いのかを、実例を交えながら具体的に解説します。
言語聴覚士の一般的なキャリアステージとは?
0〜3年:基礎力の確立期
主に病院・施設で基礎的な評価・訓練・記録業務をこなしながら、疾患や支援技術の理解を深める時期です。多職種連携や患者との関係構築など、対人スキルの土台も形成されます。
4〜6年:専門性の深掘り期
関心のある分野(例:嚥下、小児、高次脳機能障害など)を深掘りし始める時期。学会発表、認定資格取得、後輩指導への関与など、「専門職としての自立」が求められるフェーズです。
7〜10年:キャリアの転換期
現場でのスキルを武器に、「次のステップ」を考え始める人が増える時期です。管理職を目指す、訪問に転職する、大学院に進学するなど、進路の分岐点が訪れます。
5年後に目指すべきキャリアモデル
① 専門性を持つ臨床家
1つの疾患や対象に特化し、施設内外から「〇〇といえばあの人」と認知される存在へ。認定STや、関連資格の取得がキャリアの支えになります。
② 教育的立場への一歩
実習生の受け入れや新人教育に携わることで、教育者としての道も開けます。自分の経験を体系化し、他者に伝える力が求められます。
③ 組織内リーダーとして活躍
チーム内の勉強会企画、業務改善提案、後輩の育成など、リーダー的な役割を担う人材になるのも一つの方向性です。
10年後に広がるキャリアの可能性
管理職としてチームを牽引
主任・課長・室長などの役職に就き、部署運営や人材マネジメントを行う立場になります。臨床に加え、経営視点や組織づくりが求められます。
訪問・開業という独立の道
経験と人脈を活かし、訪問リハや自費リハ事業を立ち上げる人も増えています。ビジネス的視点やマーケティング力も必要になります。
大学院進学・研究職への転身
臨床を一度離れ、大学院で研究に没頭する道も。修士・博士課程を経て大学教員や研究員になる例もあります。
実例紹介|先輩STのキャリアビジョン実現ストーリー
ケース1:急性期→認定ST→大学病院へ
5年目で摂食嚥下認定ST取得。10年目には大学病院へ転職し、嚥下チームの一員に。現在は学会でも活躍中。
ケース2:地域包括施設→訪問開業
介護施設で高齢者支援に従事しながら経験を積み、8年目に訪問リハを起業。週4勤務・高単価で収入もアップ。
ケース3:小児領域→大学院→教員に
発達支援に関心を持ち、大学院で言語発達の研究へ。現在は専門学校の専任教員として教育に従事。
キャリアを描く上での注意点
- 「他人と比べない」:自分だけの道を築こう
- 「長期視点で動く」:準備には時間がかかる
- 「学びを止めない」:スキルの陳腐化に注意
まとめ:未来の自分は、今の選択から生まれる
言語聴覚士としてのキャリアは、資格を取った後からが本番です。5年後、10年後の自分が満足できるよう、日々の経験を積み重ね、学びを継続することが大切です。
他人に決められた人生ではなく、自分自身が納得できる働き方を選びましょう。未来は今の選択の積み重ねによってつくられていくのです。

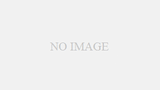
コメント