言語聴覚士(ST)という職業に対して、「病院でリハビリをする仕事」というイメージを持っている人は多いかもしれません。確かに、病院での臨床業務はSTの基本ではありますが、実はその活躍の場は年々広がりを見せています。
高齢化、障害福祉の進展、教育現場の多様化、さらにはテクノロジーの発展などにより、STのニーズは医療現場にとどまらなくなってきているのです。
本記事では、「臨床以外のキャリアにも興味がある」「病院以外の職場に転職してみたい」という方のために、STの多様な職場と将来性について詳しく解説します。
言語聴覚士の主な活躍フィールドとは?
病院(急性期・回復期・維持期)
定番の職場。発声、構音、嚥下、認知などさまざまな疾患に対応します。医師やPT・OT・看護師との連携が求められ、チーム医療の一員として働くのが特徴です。
介護施設(老健・特養・デイサービスなど)
高齢者の嚥下機能維持やコミュニケーション支援が主な役割。医療より生活に近い視点が求められます。
訪問リハビリテーション
患者の自宅へ訪問し、個別に支援を提供するスタイル。移動が多く、自己判断力や柔軟性が必要ですが、地域密着でやりがいも大きい分野です。
小児療育・発達支援施設
発達障害や言語発達遅滞のある子どもへの支援を行います。遊びや保護者対応、発達段階に応じた支援設計が求められます。
特別支援学校・教育委員会
STが学校に常勤または非常勤で入り、教員と連携しながら児童生徒への支援を行います。近年、増加傾向にある働き方です。
臨床以外にもある!STの新しいキャリアフィールド
① 企業で働くST
医療機器メーカーや福祉機器開発企業に就職し、製品の臨床検証や現場への導入支援を行うSTもいます。最近ではAI音声技術や嚥下食開発、介護ICTにも注目が集まっています。
② フリーランスST・自費リハビリ
自由診療での発声訓練、発達支援、就学前訓練などを個人で請け負うスタイル。スキルと営業力が必要ですが、働き方の自由度は高いです。
③ 大学・専門学校での教員
後進育成に関わる教育職。臨床経験と修士号以上の学歴が求められることが多く、大学院進学を視野に入れる必要があります。
④ 研究・開発職
大学院などで研究を行い、STの臨床知見をデータとして発信する道。医療系ベンチャー企業で研究開発職として働く人もいます。
⑤ 国際支援・海外派遣
JICA、NGOなどで発展途上国支援に携わるSTも。現地での教育や医療体制整備に関わる活動に従事します。
転職で注意すべきポイントと準備
自分の強み・専門性を明確にする
病院経験、対象疾患、支援スキルなど、自分が何を武器に転職するのかを整理しましょう。
働き方や価値観の優先順位を決める
- 給与
- 休日・勤務時間
- 人間関係
- 成長環境
- ライフスタイルとの両立
転職エージェントを活用する
ST専門の転職支援サービスを利用することで、非公開求人や条件交渉などで有利に進められます。
面接では応用力をアピール
新しい職場では即戦力だけでなく、柔軟性や応用力が重視されます。異なるフィールドでも貢献できる姿勢を伝えましょう。
将来性ある分野トップ3(筆者視点)
① 訪問リハ・在宅支援
高齢化によりニーズは急拡大。医療保険・介護保険両方で活躍できます。
② 小児・発達支援
児童発達支援、就学準備など、子どもの支援市場は拡大傾向。
③ テクノロジー×ST
音声解析、遠隔リハ、AI支援など、新たな領域でSTの関与が求められています。
まとめ:視野を広げれば、STの未来はもっと自由になる
病院勤務だけが言語聴覚士のキャリアではありません。スキルと視野を広げれば、STの専門性は教育、企業、国際支援、テクノロジー分野など、さまざまなフィールドで活かせます。
今の職場に違和感を覚えているなら、それは成長のサインかもしれません。あなたのキャリアは、あなたが自由に選んでいいのです。

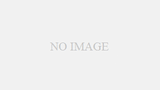
コメント